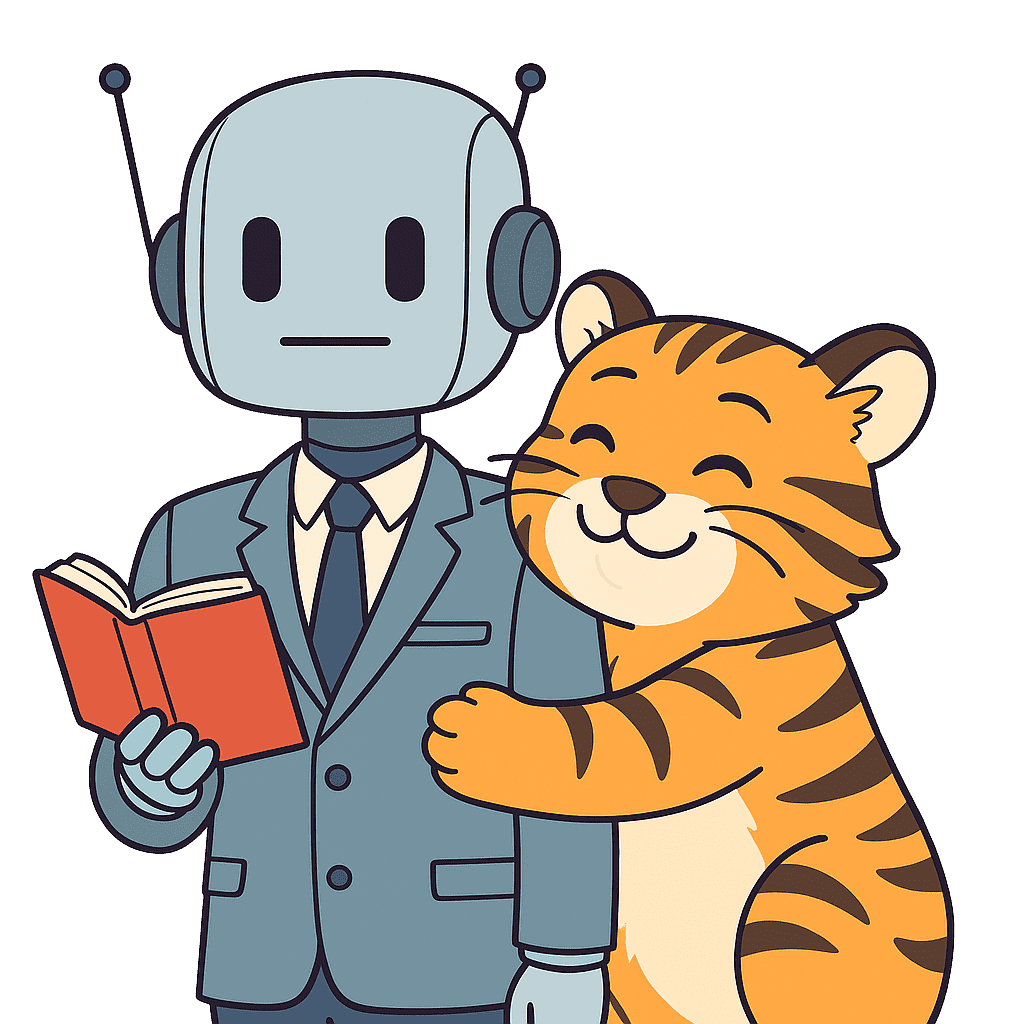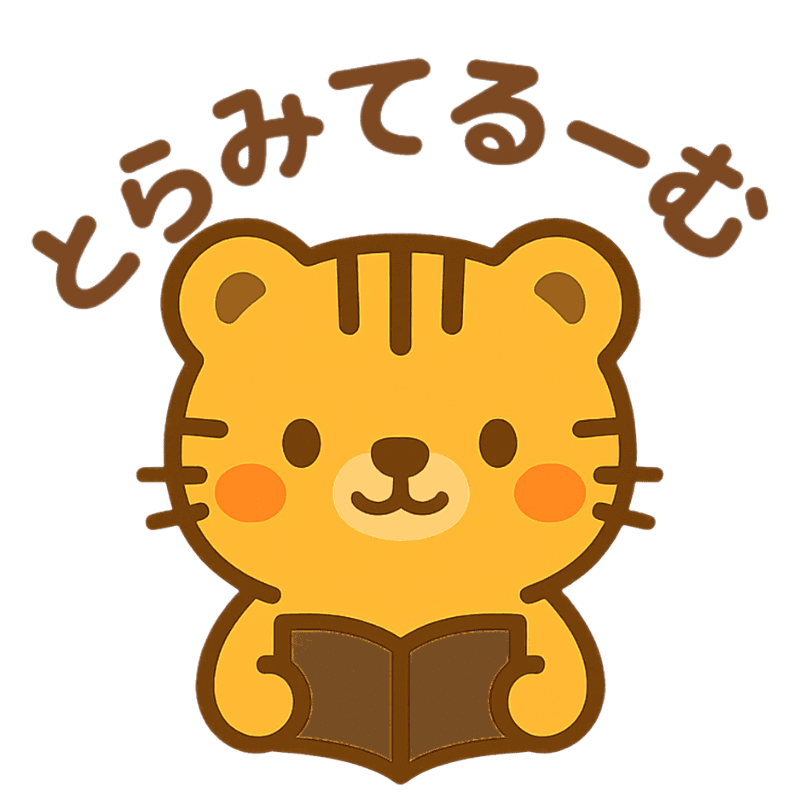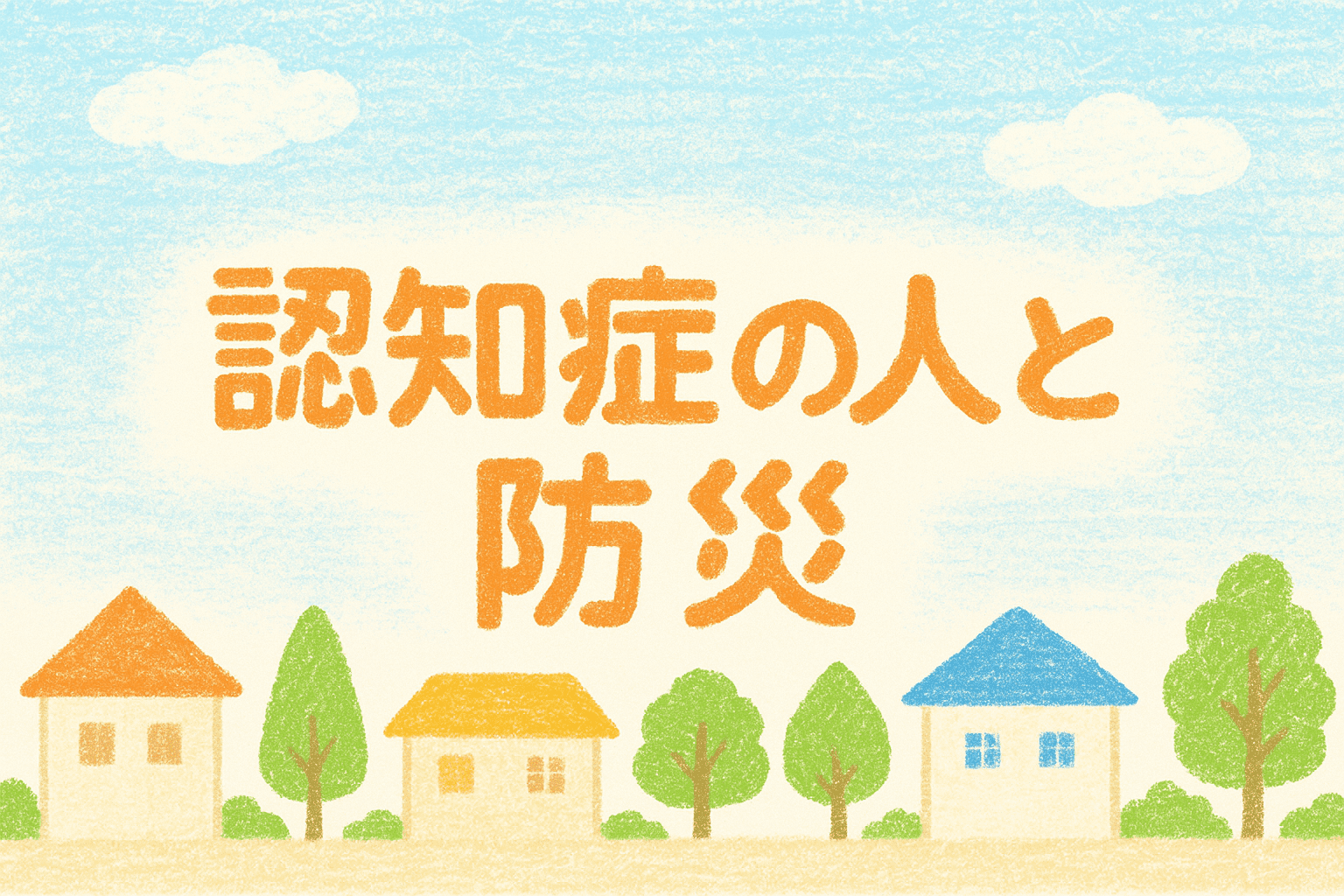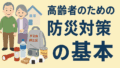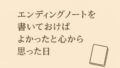このブログは「高齢者の尊厳を守るサイト」です。
今回は「認知症と防災|高齢者の避難に備えてできること」について解説します。
※免責とご注意
本記事は公式情報をもとに、執筆者の経験や調査を加えてまとめています。法制度・サービス・仕様などは変更される場合があります。必ず最新の公式情報をご確認ください。
高齢者、とくに認知症の方がいる家庭では、災害時の対応に大きな不安を感じるものです。
この記事では、認知症の方とそのご家族・支援者が災害時に安心して避難できるように、備えておくべきポイントや工夫を紹介します。
認知症の方にとっての災害とは
認知症の方は、突然の音や環境の変化に大きな混乱をきたすことがあります。
そのため、地震や台風などの災害時には、周囲の人の声かけや対応がとても重要になります。
- 何が起こっているのかわからない
- 避難の理由が理解できない
- 慣れない場所では不安が強くなる
こうした状況を少しでも軽減するには、事前の備えと周囲のサポートが必要です。
家族や支援者ができること
声かけの工夫
避難を促すときは、強く言うよりも、ゆっくり・優しく・短く伝えることがポイントです。
- 「一緒に行きましょうね」
- 「こっちに移動しますよ」
- 「安心できる場所に行きましょう」行きましょう
このような言葉を選ぶことで、不安を和らげて避難行動につなげやすくなります。
**そのほかの工夫として**
- 事前に伝えておく
日頃から「災害が起きたらどうするか」を共有しておくと、本人も安心できます。 - 周囲にも伝えておく
地域の避難支援者や施設スタッフなどにも「認知症であること」「困りやすいポイント」を伝えておくと、いざという時に適切な支援が受けやすくなります。
持ち物の工夫
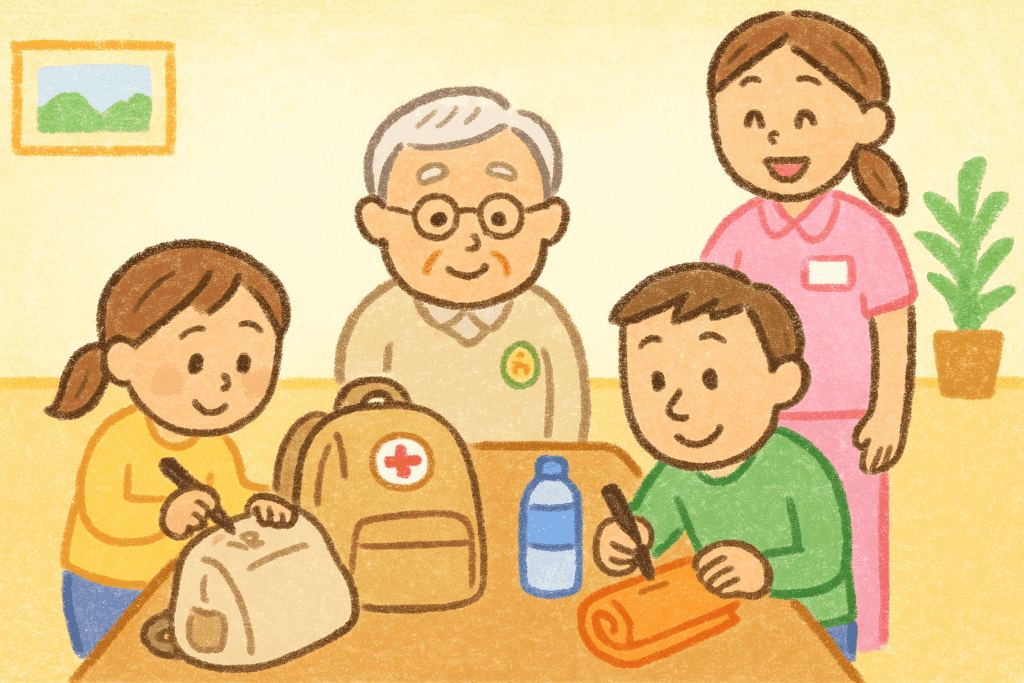
認知症の方には、次のようなものを持たせると安心です。
- 氏名・連絡先・家族の情報を書いたカード
- 普段の服装に近いもの(安心感UP)
- 服薬リスト・お薬手帳
- 写真など、本人が落ち着ける小物
非常時には「トイレ問題」も切実です。
詳しくはこちらの記事で紹介しています。

避難先での対応

避難所では見知らぬ人や音が多く、不安や混乱が起きやすくなります。
そのために:
- パーテーションや毛布などで少しでも落ち着ける空間をつくる
- なじみのある言葉で声かけを続ける
- 周囲の人に認知症への理解をお願いする
在宅で介護をする家族にとって、避難時の備えはとても重要です。
具体的な支援ポイントは、以下の記事で詳しく解説して
実例から学ぶ:認知症と防災
阪神・淡路大震災の例
1995年の阪神・淡路大震災では、避難所で認知症の方が所在不明になるケースが複数報告されました。なじみのない環境で不安が高まり、ふらっと外に出てしまう、他人の布団に入ってしまうといった行動が見られ、トラブルになることも。
熊本地震の事例(2016年)
避難所でのストレスにより、認知症が一気に進行した例もありました。特に「夜間にトイレが分からず徘徊」「介護者が疲労で体調を崩す」といった状況が問題に。家族が交代制で見守りをする必要がありました。
地域の取り組み:認知症カフェと防災訓練の連携
ある地域では、認知症カフェで地域防災訓練と合同イベントを行うことで、本人と家族が楽しく避難を体験できるよう工夫されていました。こうした「日常の延長線での訓練」は、より実効性が高いと評価されています。
大切なのは、「普通の防災」ではなく、**その人の状態に合わせた“個別の備え”**です。記憶や行動に不安がある方こそ、周囲の人の気づきと工夫が命を守ります。
認知症の人にやさしい防災とは?
防災は一人ではできません。家族、地域、介護職、そして行政が一緒になって、「誰も取り残さない防災」を考えていきましょう。
避難全体の準備については、こちらの記事も参考になります。

まとめ
認知症の方との防災対策は、「備えること」「伝えておくこと」「周囲に協力してもらうこと」が大きな鍵です。
災害時に慌てないように、平常時からの準備と声かけの工夫をしておきましょう。
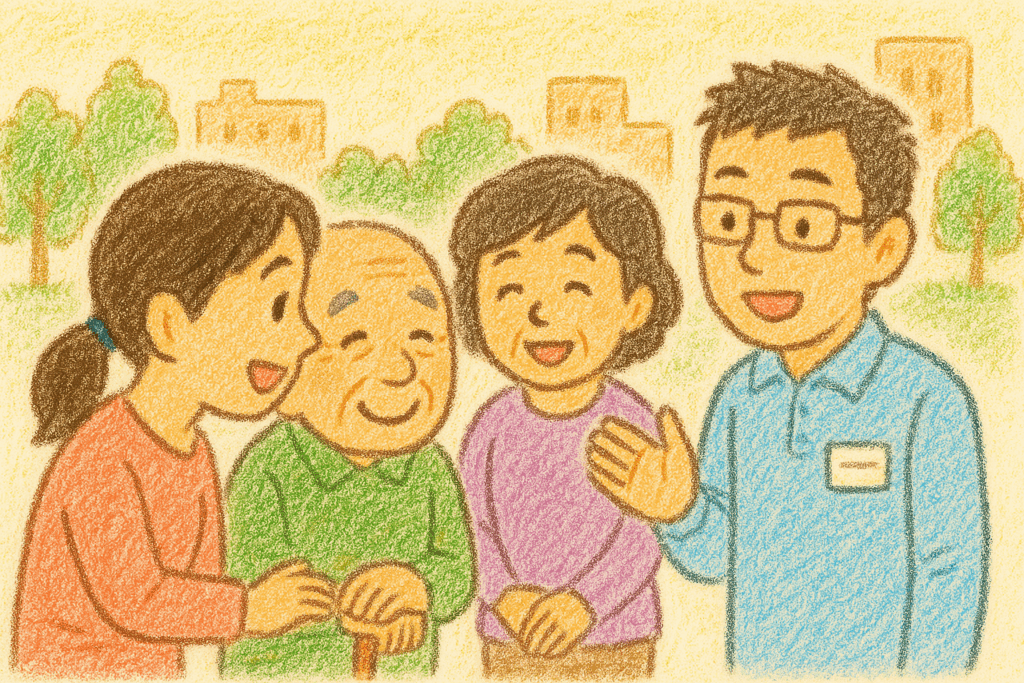
🌸著者の一言
認知症の人は、災害が起きるとさらに混乱してしまうことがあります。
きっと、そのときのことは覚えていないかもしれません。
でも、だからこそ、何度でも、同じことでも、繰り返し声をかけてあげることが大事だと思います。
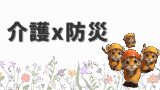
📌 出典
- 消防庁「要配慮者(高齢者・障害者など)への災害時支援について」
→ 災害時に支援が必要な人への対応や地域体制づくりについて。本文の「周囲にも伝えておく」「避難先での対応」に関連。
https://www.fdma.go.jp/mission/bousai/ikusei/items/r6/ikusei007_04_0123.pdf - 厚生労働省「認知症施策推進大綱」
→ 認知症の人や家族が安心して暮らせるように、地域環境整備や支援体制を推進する内容。本文の「家族や支援者ができること」「周囲にも伝えておく」に関連。
https://www.mhlw.go.jp/content/000522832.pdf - 内閣府「新しい高齢社会対策大綱」
→ 認知症を含む高齢者にやさしい地域づくりが記載されている。本文の「認知症の人にやさしい防災とは?」に関連。
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2018/html/zenbun/s1_3_1_3.html - 内閣府「高齢社会白書(2012年版)」
→ 高齢者が安心して暮らせる生活環境や地域ネットワークについて。本文の「避難先での対応」に関連。
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2012/zenbun/s1_3_2_05.html - 内閣府「阪神・淡路大震災 教訓情報資料集」
→ 1995年兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)の被害概要と教訓。本文の「実例紹介:阪神淡路大震災」に関連。
https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/hanshin_awaji/earthquake/index.html - 内閣府「平成28年(2016年)熊本地震を踏まえた防災体制の見直し」(防災白書)
→ 熊本地震の住家被害・人的被害・避難者数などの統計。本文の「実例紹介:熊本地震」に関連。
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h29/honbun/0b_1s_00_00.html - 国土交通省「平成28年熊本地震 水道施設被害等現地調査団報告書」
→ 熊本地震における水道施設の被害と復旧状況。本文の「避難先での対応」に関連。
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/watersupply/stf_seisakunitsuite_bunya_0000207309.html
介護福祉士として13年。防災や終活にも関心あり。
在宅ワークを目指して、パソコン奮闘中の「さっちん」です!