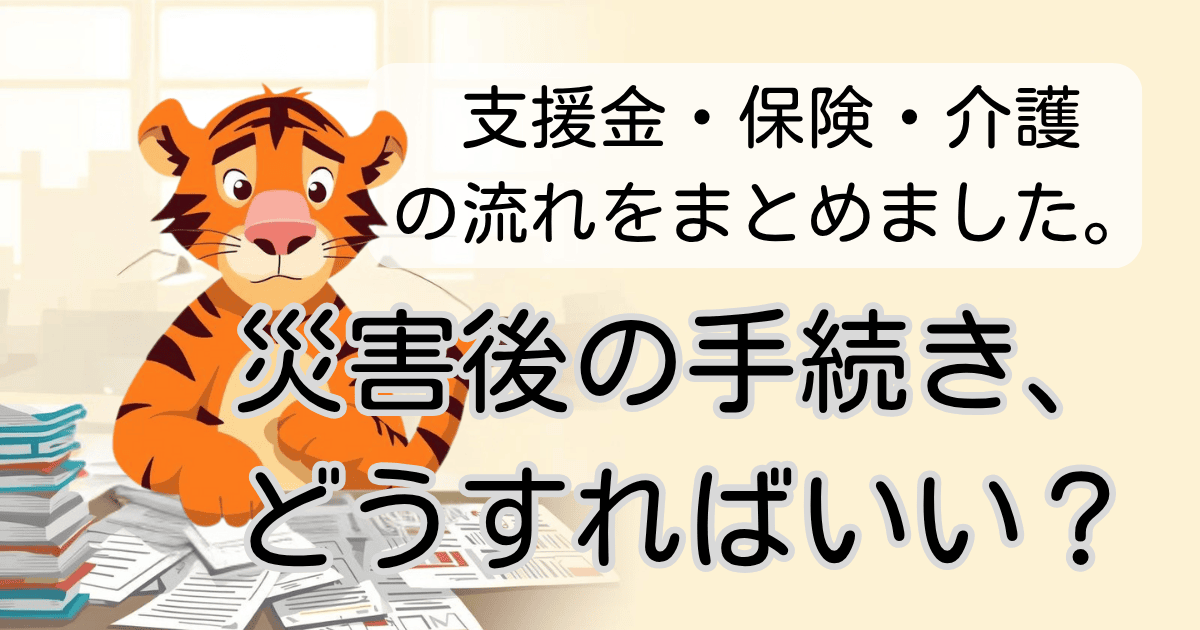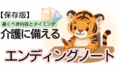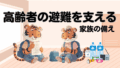このブログは「被災した人の生活と尊厳を守るサイト」
今回は「災害後に必要な手続き」についてまとめました。
※免責とご注意
本記事は公式情報をもとに、執筆者の経験や調査を加えてまとめています。法制度・サービス・仕様などは変更される場合があります。必ず最新の公式情報をご確認ください。
※本記事の内容は 2025年6月時点の情報をもとにまとめています。
災害後の生活を立て直すには、罹災証明の取得から支援金・保険・公共料金の減免、介護や住まいの確保まで、複数の手続きが連なります。まず全体像を掴んで、必要な順に申請しましょう。

ここからは、実際の手続きの話になります。
私は正直ちょっと苦手なんですけど……難しいところは、チャット先生にお願いしちゃいますね!

おまかせください。災害のあと、「どこに相談すればいいの?」「まず何を出せばいいの?」と迷う人が少なくありません。
このページでは、支援や保険、介護に関する手続きをわかりやすく整理しました。
罹災(りさい)証明書の申請

まず最初に行うのが「罹災証明書」の申請です。
これがすべての支援や保険の起点になる大切な手続きです。
申請先:市区町村
使い道:各種支援金、税・公共料金の減免、保険請求の根拠
持ち物:本人確認書類、被害写真(片付け前の全体・部位・日付)、印鑑 等
流れ:申請 → 現地調査 → 被害区分の判定 → 証明書交付
ポイント:片付けの前に写真を残す/領収書や見積も保管。
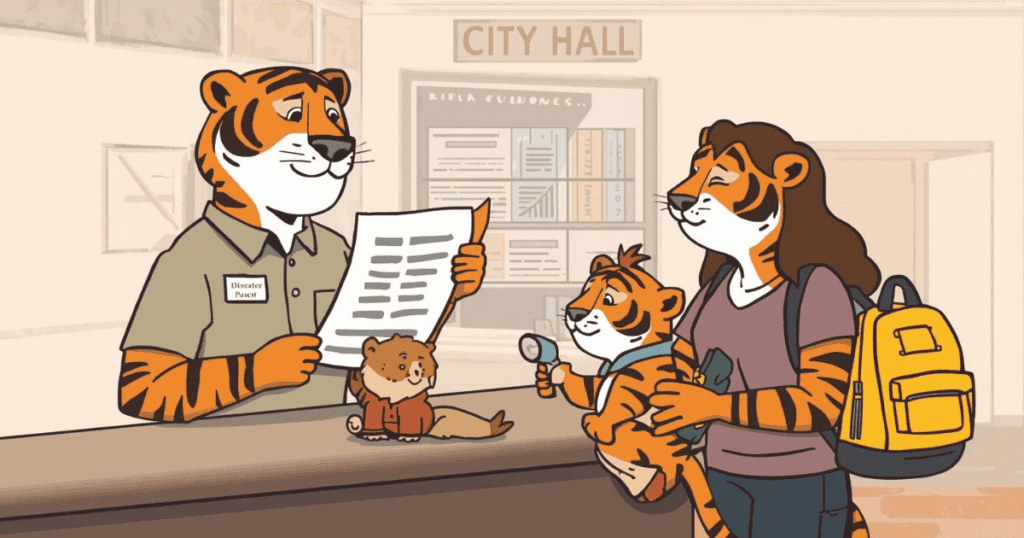
被災者生活再建支援金の申請手続き
住宅が「全壊」や「大規模半壊」と認定された場合、「被災者生活再建支援金」を受け取ることができます。
この支援金は生活の再スタートに使えるお金で、家族構成や被害の程度によって金額が異なります。
申請窓口は自治体で、罹災証明書が必要です。
本人確認書類、印鑑、振込先の通帳なども持って行くと安心です。
災害見舞金・義援金の申請手続き
自治体や日本赤十字社などから、見舞金や義援金が支給される場合があります。
これは寄付をもとに配られるお金で、被害の程度に応じて支給されることが多いです。
対象者や金額、申請方法は地域によって異なるため、お住まいの自治体に確認しましょう。

この「災害見舞金」と「義援金」は、実は仕組みがまったく違うんです。
災害見舞金は自治体や社会福祉協議会が“見舞い”として出すお金。
一方の義援金は、全国から寄せられた寄付金を分配するものです。
見舞金は申請が必要な場合が多く、義援金は罹災証明があれば自動支給の自治体もあります。
ただし、どちらも地域でルールが違うので、必ず市役所や町の福祉課で確認しましょう。申請のタイミングを逃すと、受けられるはずの支援を逃すこともありますよ。

知ってるか知らないかで、ほんとに差が出ますね。掲示板や役所のサイトを一度チェックするだけでも違います。
知っておくことで、支援がちゃんと届くんだと思います。
保険(火災・地震)災害後の請求手続き
住宅や家財が被害を受けた場合は、火災保険や地震保険の請求ができます。
まずは加入している保険会社に連絡し、被害内容を伝えましょう。
必要なものは、保険証券の番号、被害写真、場合によっては罹災証明書などです。
申請後に保険会社の調査員が現地確認に来る場合もあります。
公共料金の減免・支払い猶予
災害によって家計が厳しくなった場合、電気・ガス・水道・NHKなどの公共料金が減免されたり、支払いが猶予されたりする制度があります。
罹災証明書が必要なことが多く、各サービス会社に問い合わせて手続きしてください。

家が壊れてしまっているのに、電気や水道のことまで気が回らない──それが普通だと思います。
介護サービス・障害福祉サービスの継続手続き
介護認定や障害認定を受けている人は、災害後もサービスを受けられるように手続きが必要です。
まずは担当のケアマネジャーや利用している事業所に連絡しましょう。
避難先でも一時的にサービスを受けられるよう調整してもらえる場合があります。

高齢者や体調が悪い方は、家族やケアマネジャー、地域包括支援センターを通じて代理申請できます。
無理をせず、身近な支援者に早めに相談しましょう。
住まいの確保(避難所・仮設)
自宅での生活が難しい場合、一時的に避難所や仮設住宅の利用ができます。
申請は市区町村の窓口で行い、罹災証明書が必要になることがほとんどです。
高齢者や障害のある人などは、優先的に案内される場合もあります。

災害後の手続きをまとめて確認
ほかにも使える制度があります

災害のあとって、ただ片付けるだけじゃないんです。
手続きをすることで、お金の支援や生活の再建が受けられる制度がいくつもあります。
たとえば──
生活福祉資金(貸付):生活再建の一時資金
税・社会保険料の減免・猶予:所轄窓口に相談
被災者支援総合窓口:自治体のワンストップ相談
よくある“つまずき”を防ぐコツ
写真は片付け前に全体→部位→型番等まで撮る
領収書・見積書・やり取りメールは全部保存
本人確認書類・口座・印鑑をまとめて保管
期限のある申請(支援金等)は先に期日をメモ

知ってるか知らないかで、ほんとに差がでるんだね。ちゃんと知っておくだけで、もらえる支援や受けられるサービスが変わるんですね。
災害後の手続きが落ち着いたら、次は“備える段階”も大切です。
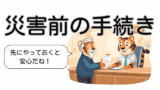
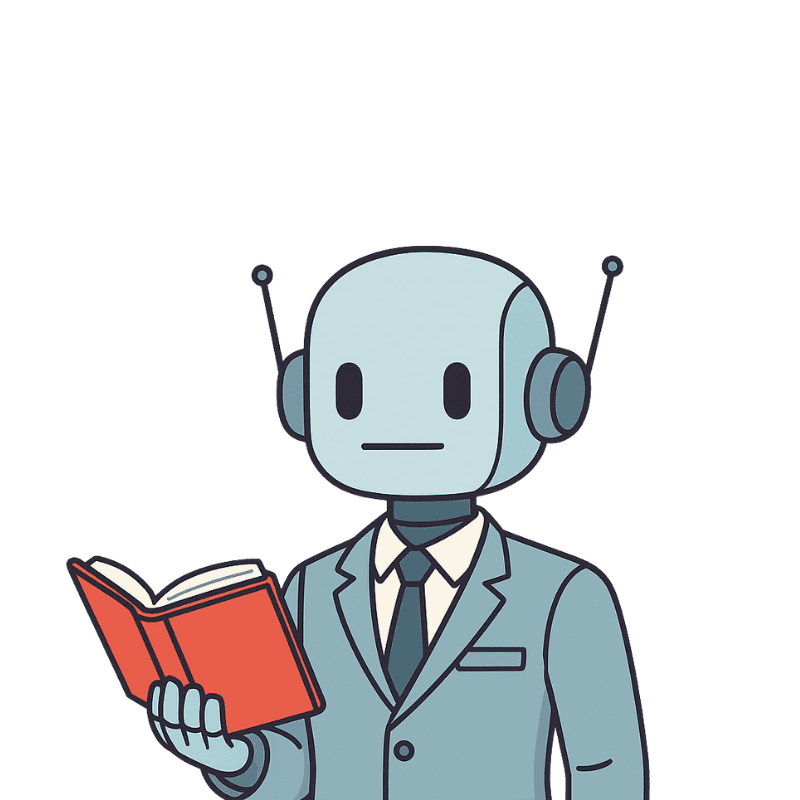
まとめ
心身の負担が大きい時期こそ、手続きの順番を意識すると動きやすくなります。
「罹災証明 → 主要な支援(支援金・保険) → 生活費の猶予・減免 → 介護・住まいの確保」の順で、できるところから進めましょう。
🌸著者の一言
災害の後、元の生活に戻るためにはたくさんの手続きをしないといけません。
「めんどうくさい」なんて言っていられないのだな、と感じます。知っていれば受け取れるお金や支援もあります。
だからこそ、少しでも情報を知っておくことが大事だと思います。

📚 出典
・内閣府「罹災証明書Q&A」
https://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/higai_qa.pdf
・厚生労働省「高額療養費制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/index.html
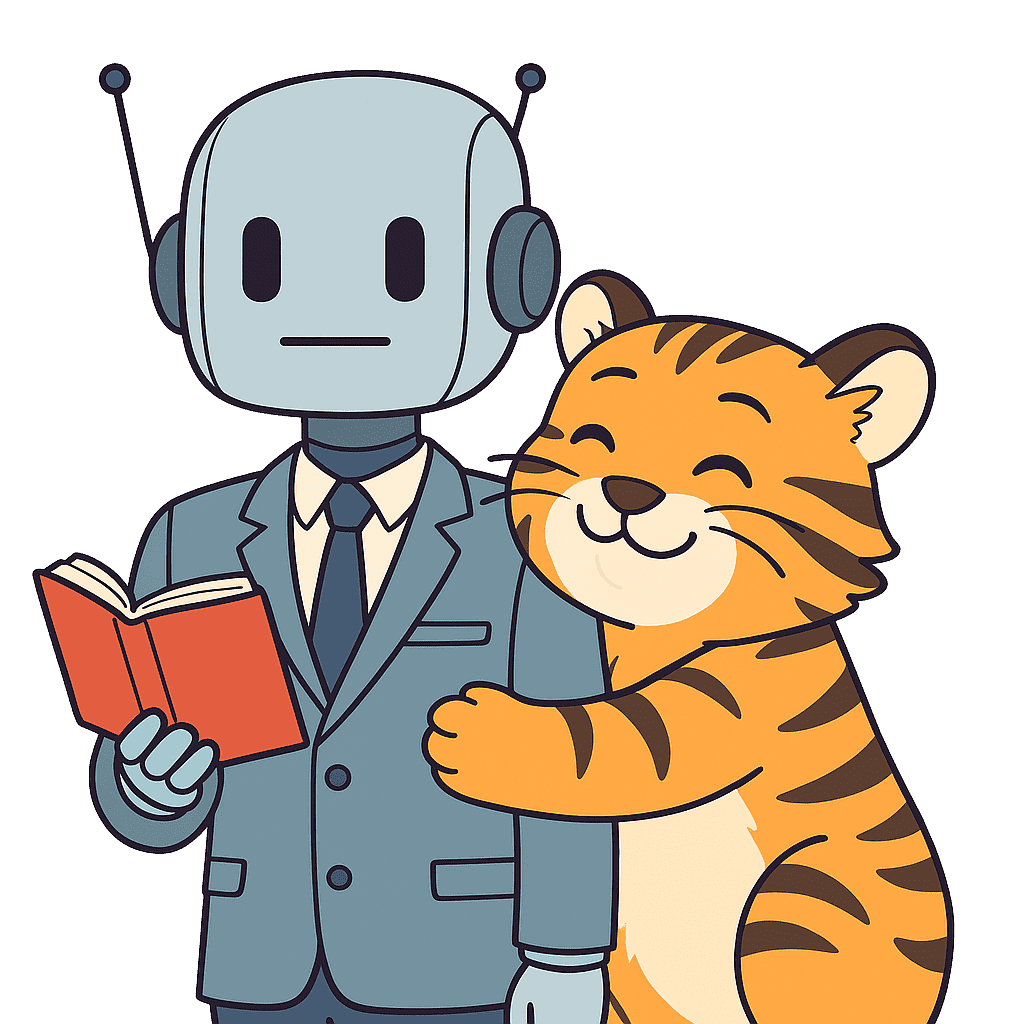
介護福祉士として13年。防災や終活にも関心あり。
在宅ワークを目指して、パソコン奮闘中の「さっちん」です!
※本記事は2025年6月時点で確認した情報をもとにしています。