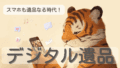このブログは「ペットと高齢者の命を守るサイト」です。
今回は、災害時にペットと一緒に避難するための備えについて解説します。
※免責とご注意
本記事は公式情報をもとに、執筆者の経験や調査を加えてまとめています。法制度・サービス・仕様などは変更される場合があります。必ず最新の公式情報をご確認ください。
※本記事の内容は 2025年5月時点の情報をもとにまとめています。
私は介護の仕事をしています。
もし今、大きな災害が起きたら——
高齢者と一緒に安全に避難できるだろうか?と考えることがあります。
加齢によって体力や筋力が落ちると、避難に時間がかかったり、階段の昇り降りが難しくなったりします。
そんな状況を想像したとき、もう一つ大切な存在に気づきました。
それが「ペット」です。
ペットも家族の一員だからこそ、人と同じように守る準備が必要です。
この記事では、災害時に高齢者とペットが安心して避難するためにできる備えをまとめました。
介護・防災・動物愛護の視点から、いっしょに考えていきましょう。
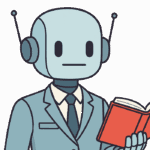
ここからは私が説明していきます。
ペット避難の基本
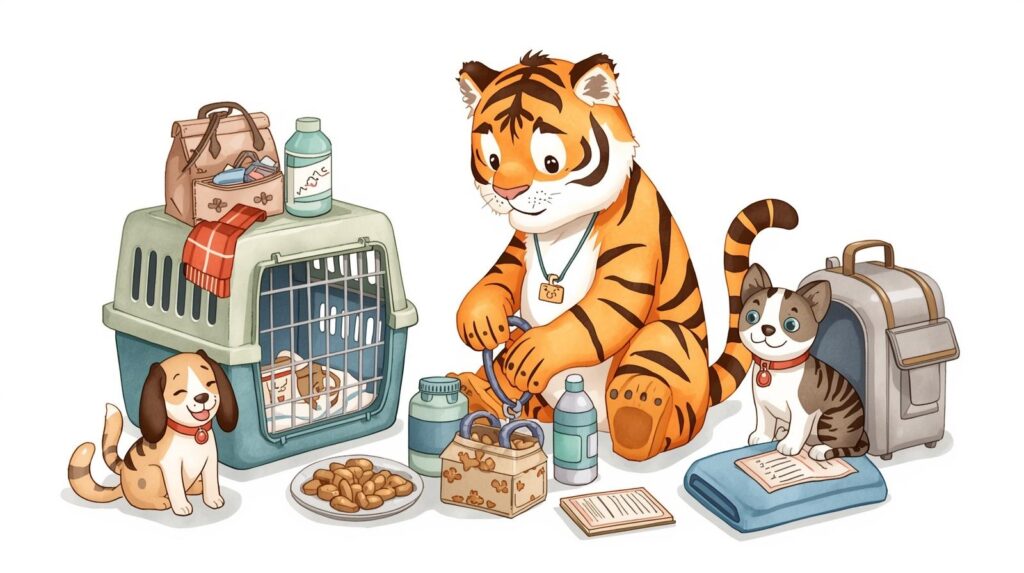
- キャリーケースやケージの準備
- リード・首輪・迷子札
- フード・水(最低3日〜1週間分)
- ペットシーツ・猫砂などトイレ用品
- ワクチン接種証明書や健康手帳
高齢者とペットの避難|自治体ごとの対応の違いペットと一緒に避難できる?自治体ごとの対応の違い
私自身、災害時にどうなるかを考えたとき、「ペット同行避難」という言葉が気になりました。
最近はこの言葉も少しずつ広がっていますが——
たとえば、ある市ではペット同伴スペースが屋内に設けられている一方で、
別の市では屋外や別室に分けられている場合もあります。
特に高齢者世帯では、屋外スペースでの避難は体力的にも健康面でも大きな負担になることがあります。
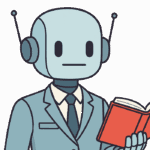
だからこそ、自分の住む地域のルールを事前に確認し、ペットと高齢者の命を守る準備をしておくことが大切です。
実践ポイント
- 市区町村の「防災ガイド」「動物避難マニュアル」を確認
- 検索例:「明石市 ペット同行避難」
- 自治体によって対応が大きく違うことを前提に備える
ケース別ペット避難
高齢者とペットの避難で直面する課題
特に介護中の家庭では、ペット避難はより慎重に考える必要があります。
なぜなら、抱っこやケージの持ち運びが難しいこと、鳴き声や排泄に周囲が敏感になること、さらに避難中の体調変化への不安など、現実的で深刻な課題が多いからです。
しかし、事前に準備や役割分担を決めておけば、ペットと高齢者の命を守りながら安心して避難できる可能性が高まります。

ペットも家族、どちらも守りたい。
備えポイント
- 誰がペットを連れて移動するかを事前に決める
- 福祉避難所に受け入れ可か問い合わせておく
- ケアマネージャーや訪問介護ヘルパーにも情報共有する
子どもとペットを守る避難の工夫
幼児や小さな子どもがいる家庭では、子どもの世話とペットの世話が重なり、大人に大きな負担がかかります。
そのため、避難所では鳴き声や衛生トラブルを防ぐ工夫が欠かせません。
たとえば、子どもの遊び道具やおもちゃを持参して気を紛らわせたり、ペット用トイレを準備して周囲への配慮を徹底することが、結果的に家族全員の安心を守ることにつながります。
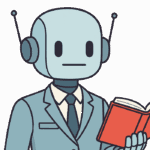
災害時は、いつもと違う環境で過ごすことになります。
これは人間にとっても、そしてペットにとっても大きなストレスです。
安心できる場所や匂いが変わるだけでも、不安を感じるのは自然なことです。
多頭飼いのペットを守る避難準備

犬や猫を複数飼っている家庭では、避難時の負担が一層大きくなります。
なぜなら、避難所は「1世帯=1スペース」と決められていることが多いため、全頭を収容できないケースもあるからです。
そのため、事前に複数の避難先や運搬方法を考えておくことが大切です。
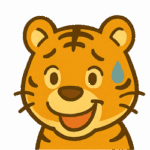
家族が多いのは心強い反面、災害時はみんなの安全を考えるだけでも本当に大変ですよね。
多頭飼いチェックリスト
- 頭数分のキャリー・ケージを用意
- フードと水は1匹あたり3〜7日分 ×頭数
- 避難所で収容できない場合に備え、ペットホテルや知人宅も候補に
- キャスター付きキャリー、折り畳みケージ、リュック型キャリーで運搬を工夫
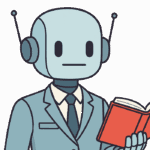
多頭飼いの場合は、それぞれの性格や関係性を考えた避難準備が必要です。
普段は仲良く過ごしていても、避難所という慣れない環境では、
ストレスから思わぬ行動を取ることもあります。
👉 避難所生活に必要な物をまとめたチェックリストはこちらも参考になります。
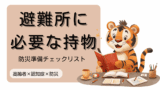
避難所でのトラブルを減らし安心を守る工夫
災害時に避難所へ入ると、他のペットや人と近い距離で過ごすため、環境ストレスが大きくなります。
その影響で、鳴き声・排泄・発情期の行動などがトラブルにつながることもあります。
一方で、普段からのしつけに加え、避妊・去勢手術を検討することで落ち着きやすくなるケースもあります。
ただし、最終的な判断は飼い主の考えや獣医師の助言に基づいて行いましょう。
こうした工夫が、避難所での安心を守ることにつながります。
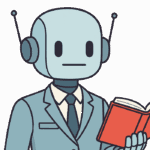
避難所では、限られたスペースで多くの人やペットが一緒に過ごします。
そのため、鳴き声や臭い、行動の違いがストレスの引き金になることがあります。
👉 高齢者や要介護の家族がいる場合、避難先でのトイレ問題も課題になります。
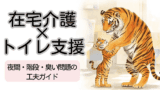
災害時、高齢者とペットが一緒に避難するときの忘れがちな備え
- 常用薬・お薬手帳のコピー(+投薬スケジュール)
- ペットと一緒に避難できる施設リスト(自治体HP・動物愛護センターを調べて印刷)
- 排泄グッズ(大人用おむつ・便座カバー・使い捨ておしりふき)
- 介護用ネームタグ・情報カード(認知症や持病ありの場合)
- 耳栓・アイマスク(騒がしい避難所での不眠対策)
- 滑り止め手袋・使い捨て手袋・手指消毒などの介助用品
- 癒しグッズ(ぬいぐるみ・香り袋など、精神的な安定に役立つもの)
エンディングノートにペットのことを書いて命を守る
もし飼い主に万一のことがあった場合、ペットの行き先が決まっていないと大きな混乱につながります。
だからこそ、エンディングノートにペットの情報を記録しておくことが大切です。
性格・健康状態・かかりつけ病院・誰に託すかなどをあらかじめ書いておけば、家族や周囲の人が安心して引き継げます。
この準備は、ペットの命と暮らしを守ることにつながります。
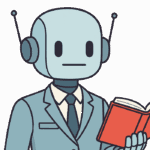
ペットの未来は、飼い主の「今のひと手間」で守れます。
書き残すことは、愛情を形にする行動です。
ペット葬と心のケアで家族の気持ちを守る

災害や病気でペットを亡くすケースも想定しておくことで、突然の事態にも落ち着いて対応しやすくなります。
そのため、ペット葬や火葬の方法をあらかじめ調べておくことは、飼い主や家族の心の支えになります。
心のケアについて
大切なペットを失ったときに感じる「ペットロス」は、誰にとっても自然な感情です。
だからこそ、避難生活の中でも気持ちを共有したり、供養を通じて心を整理することが大切です。
また、必要に応じて動物愛護団体や相談窓口などの支援を利用することが、心を守る手助けになります。
🌸著者の気づき・体験から
実際に「ペットと一緒に避難すること」を想像してみました。
キャリーに入れようとしたら嫌がって鳴いてしまう、荷物と一緒に抱えるととても重い、避難所で周囲の視線が気になる…。
つまり、頭の中でシミュレーションするだけでも準備不足に気づかされました。
特に介護中の家族がいる家庭では、「誰がペットを運ぶのか」をあらかじめ決めておくだけでも安心につながります。
たとえ実際の体験がなくても、「もし災害が起きたら」と想像すること自体が、大事な備えになると強く感じました。
ペットも人と同じ大切な家族です。だからこそ、いざという時に慌てないように想像力を働かせ、日常の中で少しずつ準備を整えておきたいですね。
その積み重ねが、ペットと人の命を守ることにつながるのだと思いました。
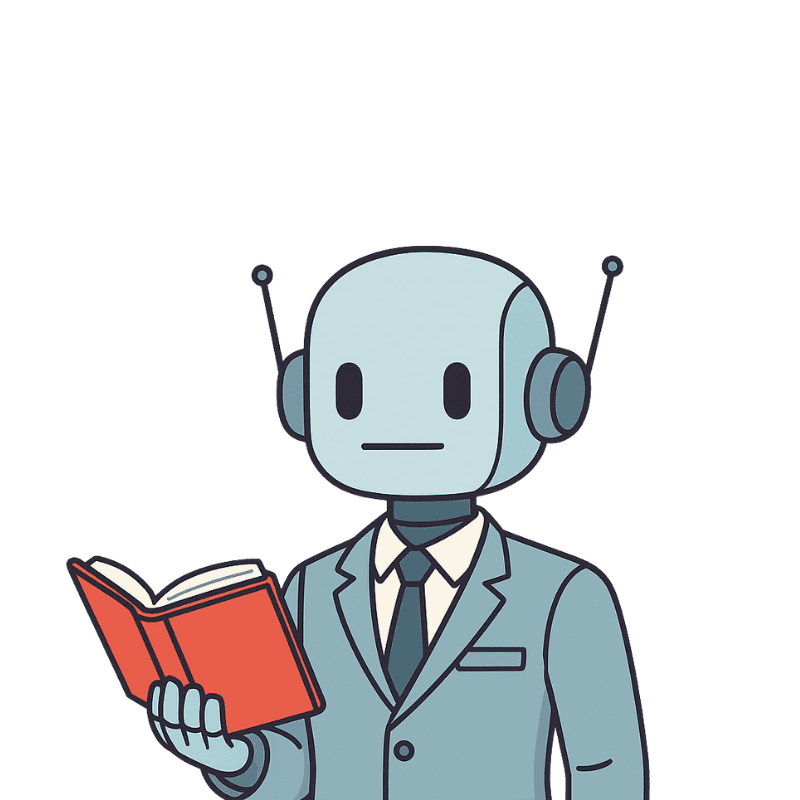
まとめ
ペットは大切な家族です。だからこそ、災害時も人と同じように「命を守る準備」が欠かせません。
基本の備えに加えて、高齢者・子ども・多頭飼いなどケースごとの工夫を考えることで、安心して避難できる可能性が高まります。
また、忘れがちな薬や排泄グッズ、情報カード、癒しグッズも大切な備えです。
さらに、エンディングノートやペット葬・心のケアを考えておくことは、家族全員の安心を守る支えになります。
結局のところ、「もしものとき、うちの子をどう守るか」を想像することが最初の一歩です。
今日から少しずつ準備を進めていけば、大切な家族と共に、より安心できる避難を実現できるでしょう。
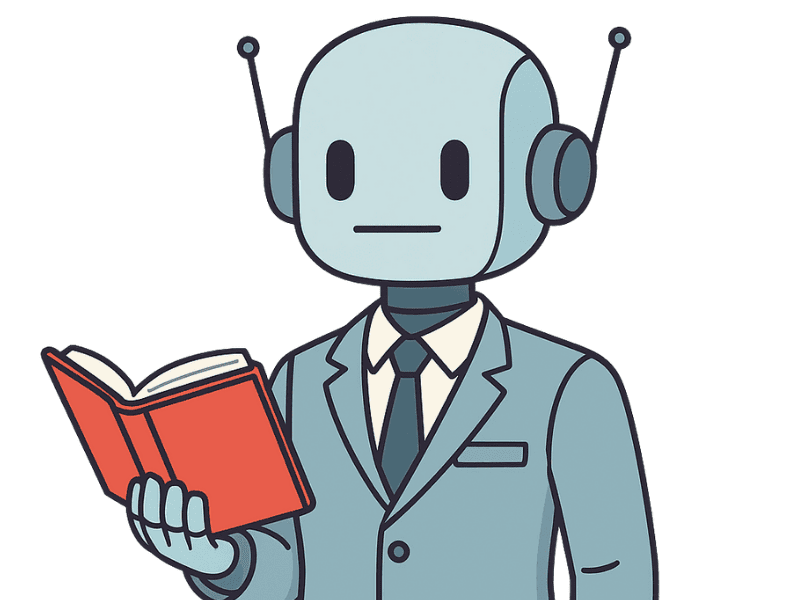
👉 在宅介護をされているご家庭では、ペットと一緒の避難が必要になる場合もあります。
ペットの具体的な内容は含まれていませんが、在宅介護の防災準備全般としてご覧いただけます。
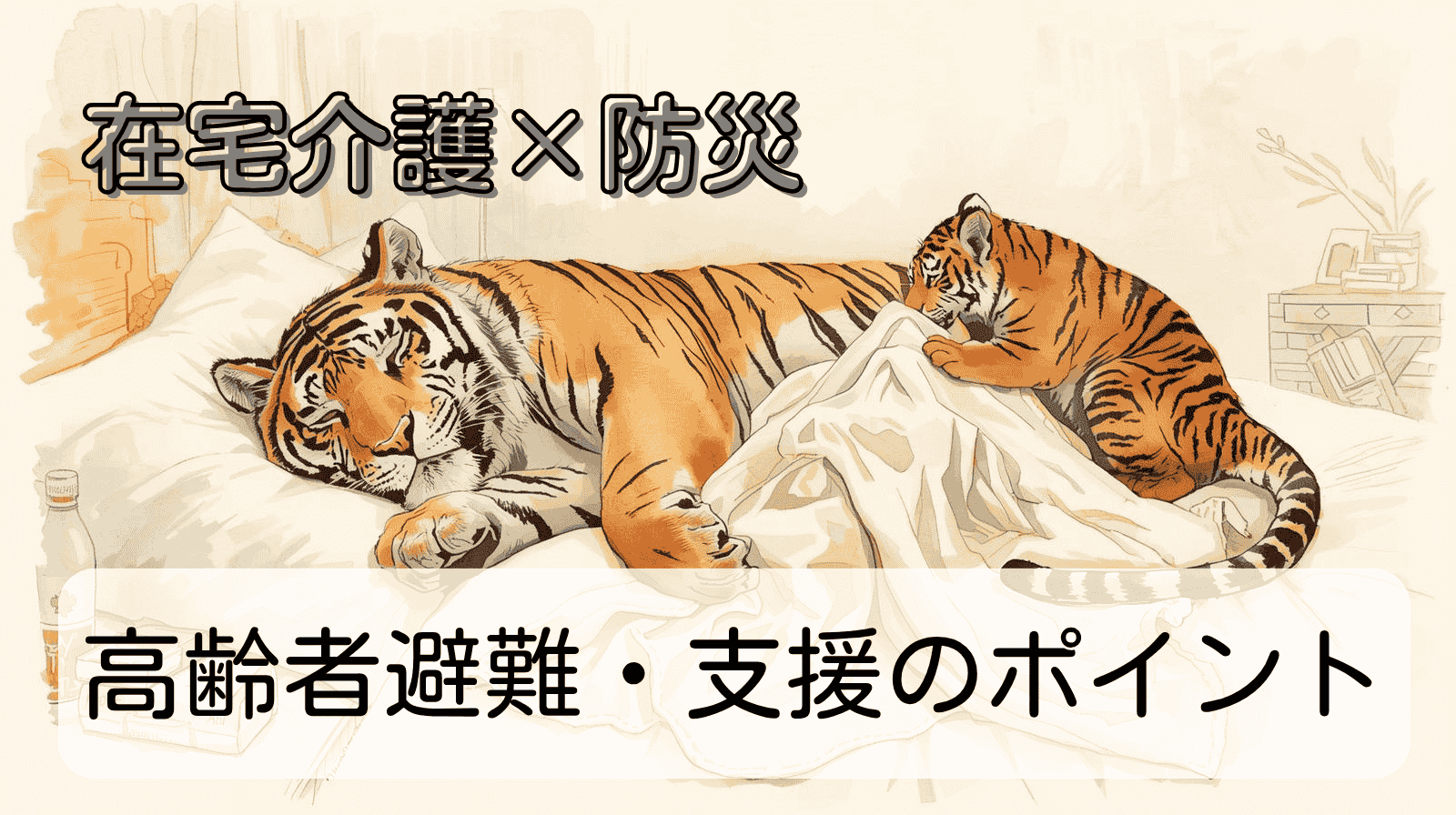
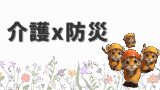
📚 参考・出典
内閣府「高齢者の転倒予防ガイド」 https://www8.cao.go.jp/kourei/
東京都防災「避難所運営マニュアル」 https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/
エステー「介護空間の複合臭に関する調査」 https://products.st-c.co.jp/plus/question/10212/
ケアニュース「ポータブルトイレの臭い対策」 https://www.care-news.jp/
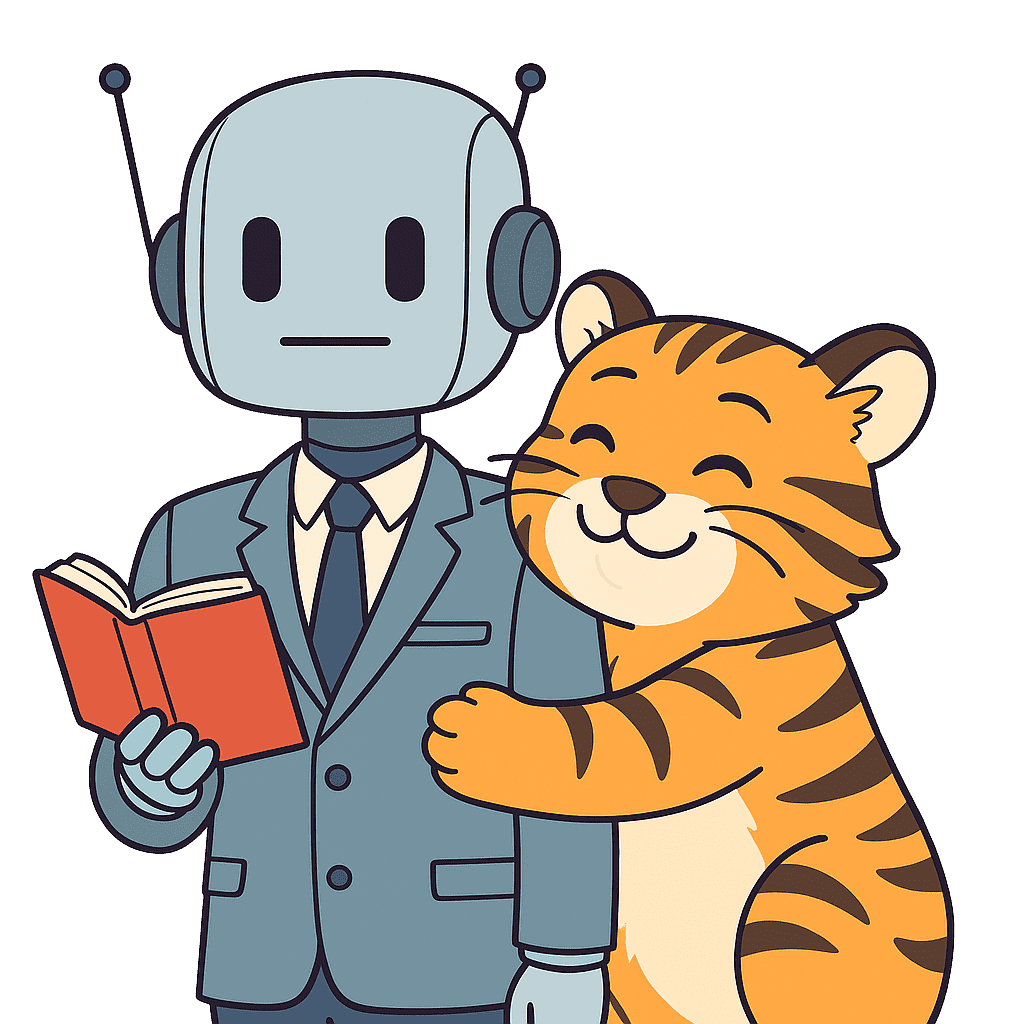
介護福祉士として13年。防災や終活にも関心あり。
在宅ワークを目指して、パソコン奮闘中の「さっちん」です!
※本記事は2025年5月時点で確認した情報をもとにしています。