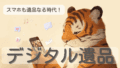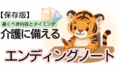このブログは「高齢者を守る」サイトです。
今回は「高齢者の防災対策の基本」について解説します。
※免責とご注意
本記事は公式情報をもとに、執筆者の経験や調査を加えてまとめています。法制度・サービス・仕様などは変更される場合があります。必ず最新の公式情報をご確認ください。
※本記事の内容は 2025年5月時点の情報をもとにまとめています。
災害は誰にとっても大きな負担ですが、高齢者にとっては特に深刻です。
体力の低下や持病、移動の難しさなどが重なり、避難が遅れたり、避難所での生活が難しくなることがあります。
だからこそ、在宅介護の家庭でも“その人に合った避難方法”を考えておくことが大切です。
高齢者が災害時に直面するリスク
高齢者は、災害時に次のような課題を抱えやすいとされています。
- 体力や筋力が落ちており、長距離の移動や階段が負担になる
- 持病や服薬があり、薬や医療機器を欠かせない
- 情報を素早く受け取れず、避難が遅れてしまう
- 一人暮らしの場合、支援が届きにくい

こうしたリスクを踏まえて、日常の延長でできる備えを意識することが大切です。
日常からできる備え

防災は「特別なこと」ではなく、毎日の生活に少し工夫を加えるだけでも安心につながります。
- 飲料水や保存食を3日分以上備蓄する
- 常備薬やお薬手帳のコピーをまとめておく
- 懐中電灯や予備電池を準備する
👉 関連記事もどうぞ:
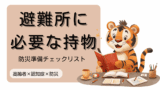
自宅と避難先の確認
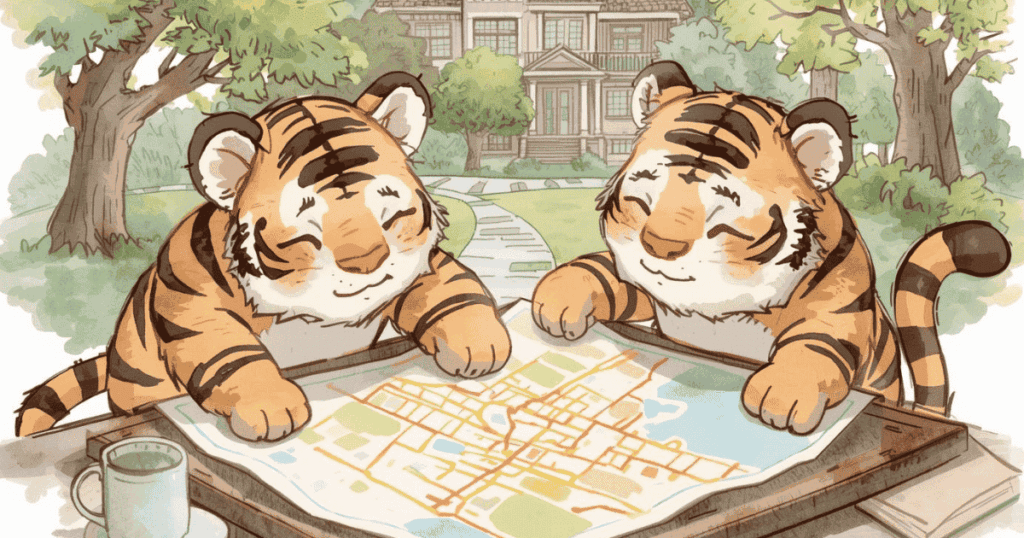
自宅の安全対策も防災の基本です。
- 家具を固定して転倒を防ぐ
- 窓に飛散防止フィルムを貼る
- 避難経路に物を置かない
また、近所の避難所や、介護が必要な人のための「福祉避難所」をあらかじめ確認しておきましょう。

各自治体の防災マップや役所の福祉課で情報が確認できます。
ご近所さんとの連携も大切
災害時は、まず「その場にいる人どうし」で助け合うことが多くなります。
高齢者の場合、近所の人とのつながりがあるかどうかが安全につながる大きな要素です。
- 日頃から顔見知りになっておく
- 緊急時に声をかけてもらえるようお願いしておく
- 安否確認の合図(声かけ・ライト点灯など)を決めておく
- 自治会や町内会の防災訓練に一緒に参加する

「共助」の意識を持つことで、一人では難しい避難や物資確保もスムーズになります。

最近は、近所にどんな人が住んでいるのか知らない――そんな話を耳にすることも増えました。
私もこれからは、近所の人に会ったら、まずは笑顔で挨拶するところから始めようと思います。
高齢者と一緒にできる防災訓練のすすめ
災害は突然やってきます。いざという時に慌てないためには、普段から「訓練」をしておくことが大切です。
特に高齢者の場合は、実際に体を動かしてみることで「できること・できないこと」が見えてきます。
✔ 避難経路を一緒に歩いてみる
✔ 非常持ち出し袋を実際に背負ってみる
✔ 懐中電灯や非常用ライトを点けてみる
✔ 電話がつながらない場合の連絡方法を確認する
小さな訓練を繰り返すことで、万一の時も落ち着いて行動できるようになります。

自治体が実施している防災訓練や避難訓練に参加するのもおすすめです。
家族や介護者と話し合っておくこと
災害は突然やってきます。事前に家族や介護者と話し合いをしておくと、慌てずに行動できます。
- 誰が付き添うのか
- どこで合流するのか
- 連絡が取れない時の方法(掲示板や安否確認サービス)
特に一人暮らしの高齢者は、近所の人や地域包括支援センターに相談しておくと安心です。
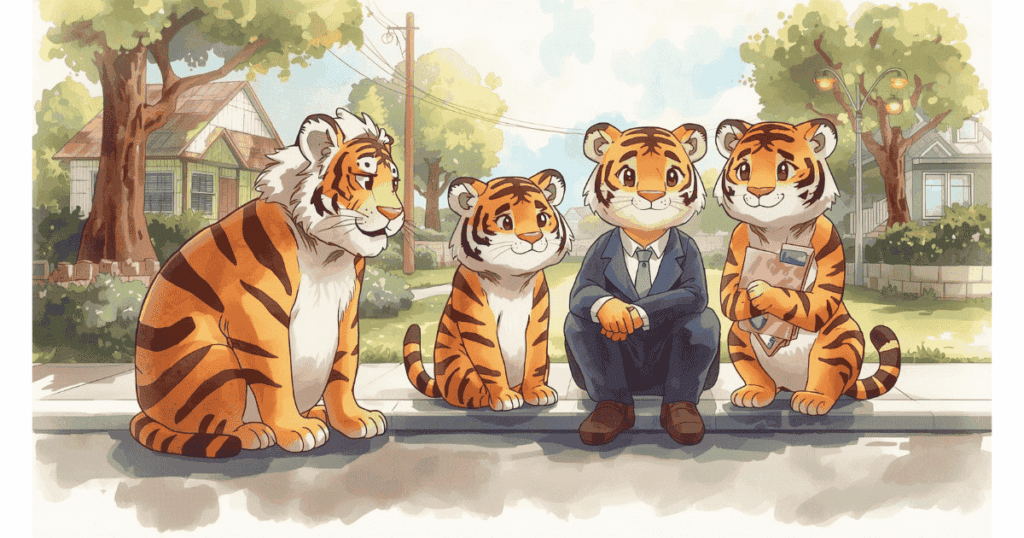
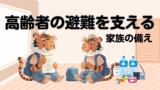
まとめ
高齢者の防災は「特別な準備」ではなく、日常生活の延長でできる小さな工夫が大切です。
今日から少しずつ備えておくことで、災害時の不安を大きく減らせます。
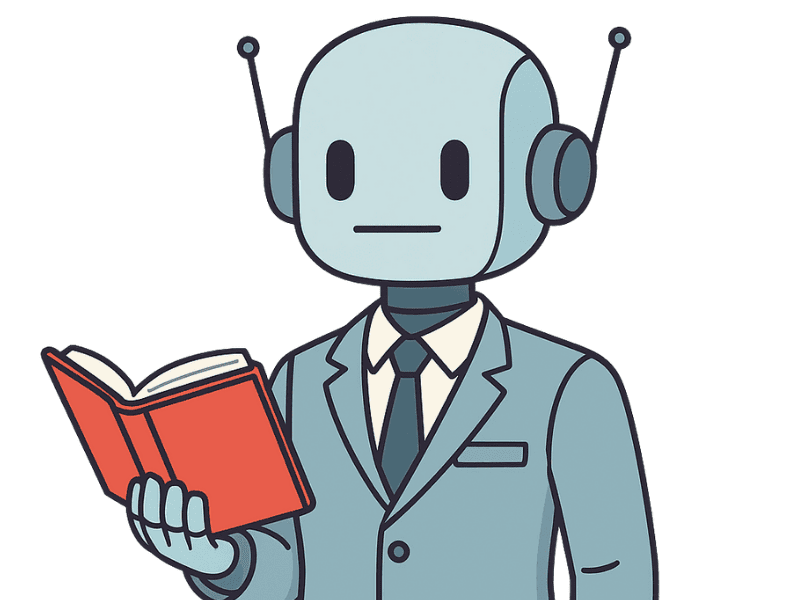
📌 体験談
いつ避難所に行くことになっても良いように、普段からこまめに入浴するようにしています。
停電に備えてスマホや充電器は常に満タンに。
特に過去の台風時、夏の停電は乾電池式の扇風機に本当に助けられました。
また、停電すると自動で点灯するコンセント常備ライトを設置しています。
以前停電が起きたときにすぐ点灯し、とても安心できました。」
こうした小さな備えが、いざという時に大きな違いを生みます。
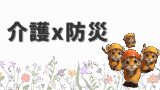
📌 出典
- 内閣府「避難行動要支援者の避難行動支援に関すること」
高齢者や障害者など、自力での避難が難しい人を支援する仕組みについて。
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/yoshiensha.html - 内閣府「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」
名簿や個別避難計画など、制度的な枠組みについて。
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/youengosya/r3/index.html - 厚生労働省「高齢者・障害者等の要配慮者に関する 防災と福祉の連携」
福祉分野と防災分野の連携、避難確保計画や個別避難計画について。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001075647.pdf
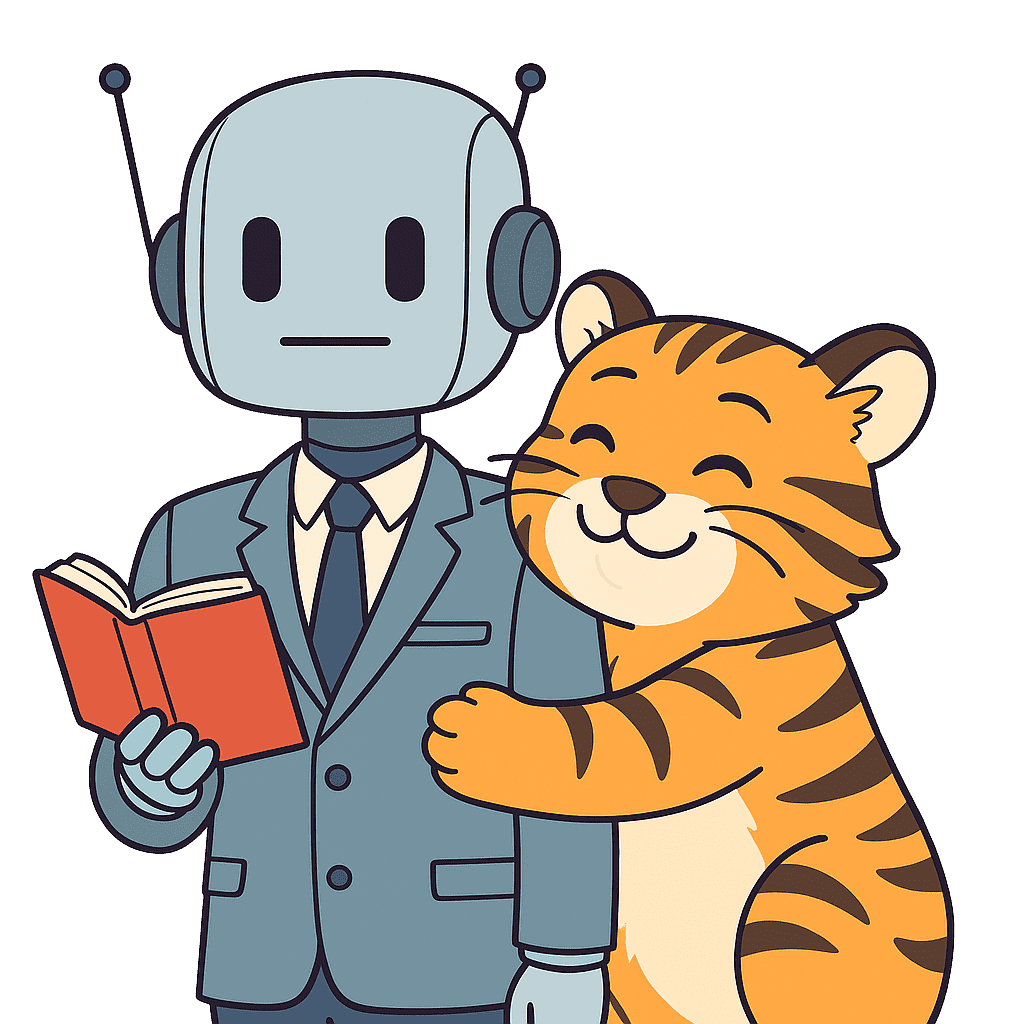
介護福祉士として13年。防災や終活にも関心あり。
在宅ワークを目指して、パソコン奮闘中の「さっちん」です!
※本記事は2025年5月時点で確認した情報をもとにしています。