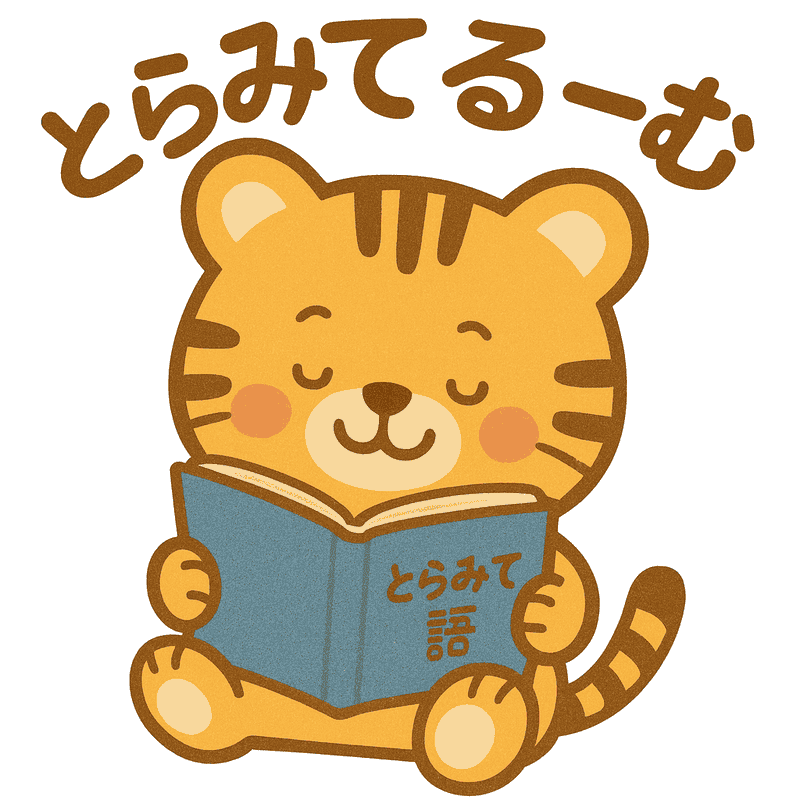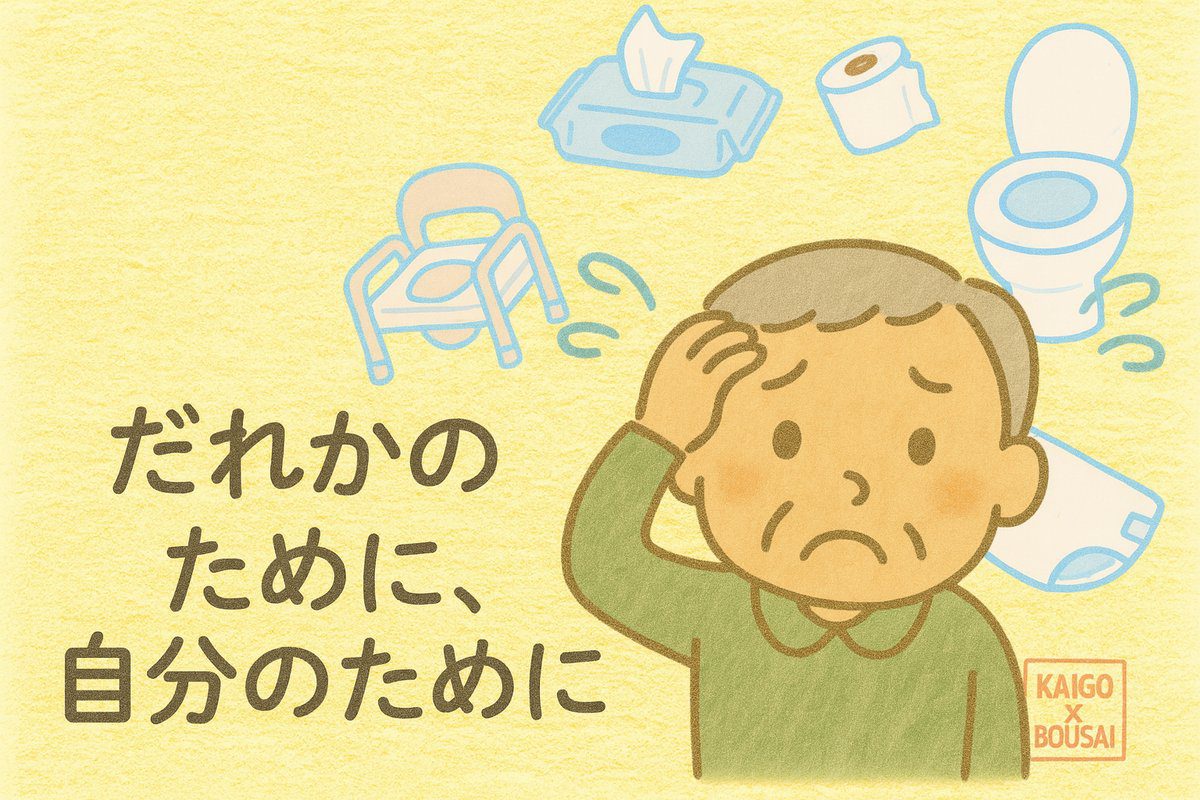はじめに:災害時、見落とされやすい「認知症の人のトイレ問題」
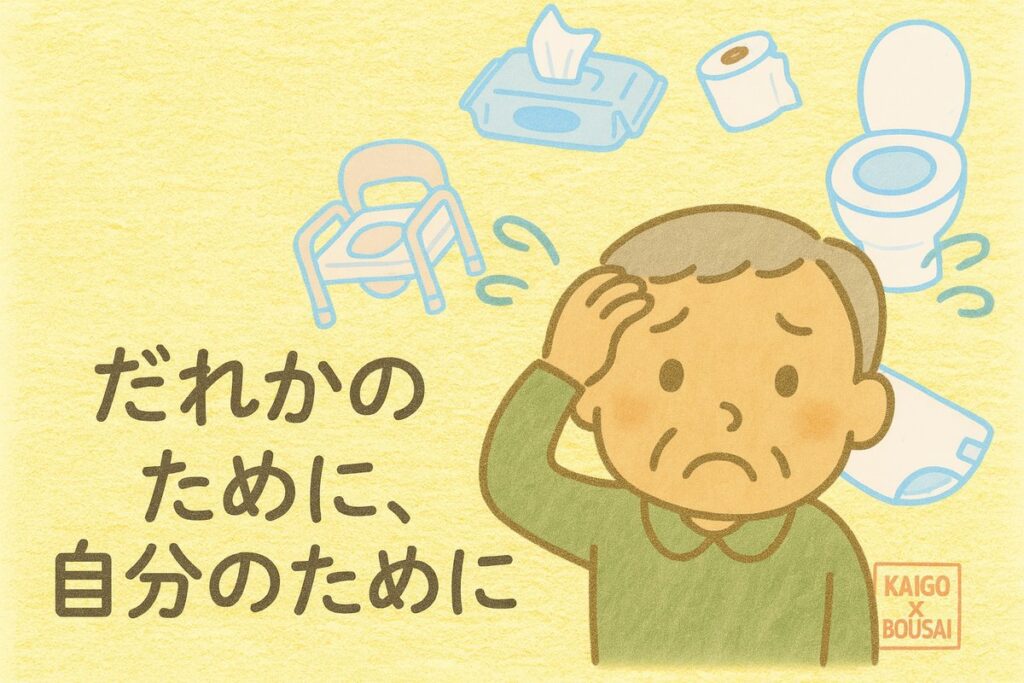
災害時、認知症の方のトイレ環境づくりは「見えにくい課題」のひとつです。
避難所でも在宅避難でも、「トイレの場所がわからない」「何をすればいいかわからない」といった混乱が起きがちです。
この記事では、認知症の人が安心して排泄できる環境を整える工夫と、家族・支援者にできるサポートを紹介します。
特に認知症の人が災害時に直面する排泄の困難に焦点を当てています。
認知症の人が排泄で混乱しやすい理由とは?

認知症の方にとって、トイレ環境の変化は大きなストレスになります。
- トイレの場所が変わると認識できない
- 明るさや音・においで不安を感じやすい
- 恥ずかしさや混乱で「行きたくない」と拒否する
- 周囲の視線や音に敏感に反応してしまう
そのため、災害時には本人の「感覚」と「記憶」に合わせた環境調整が必要です。
避難所で安心できる排泄空間をつくる工夫
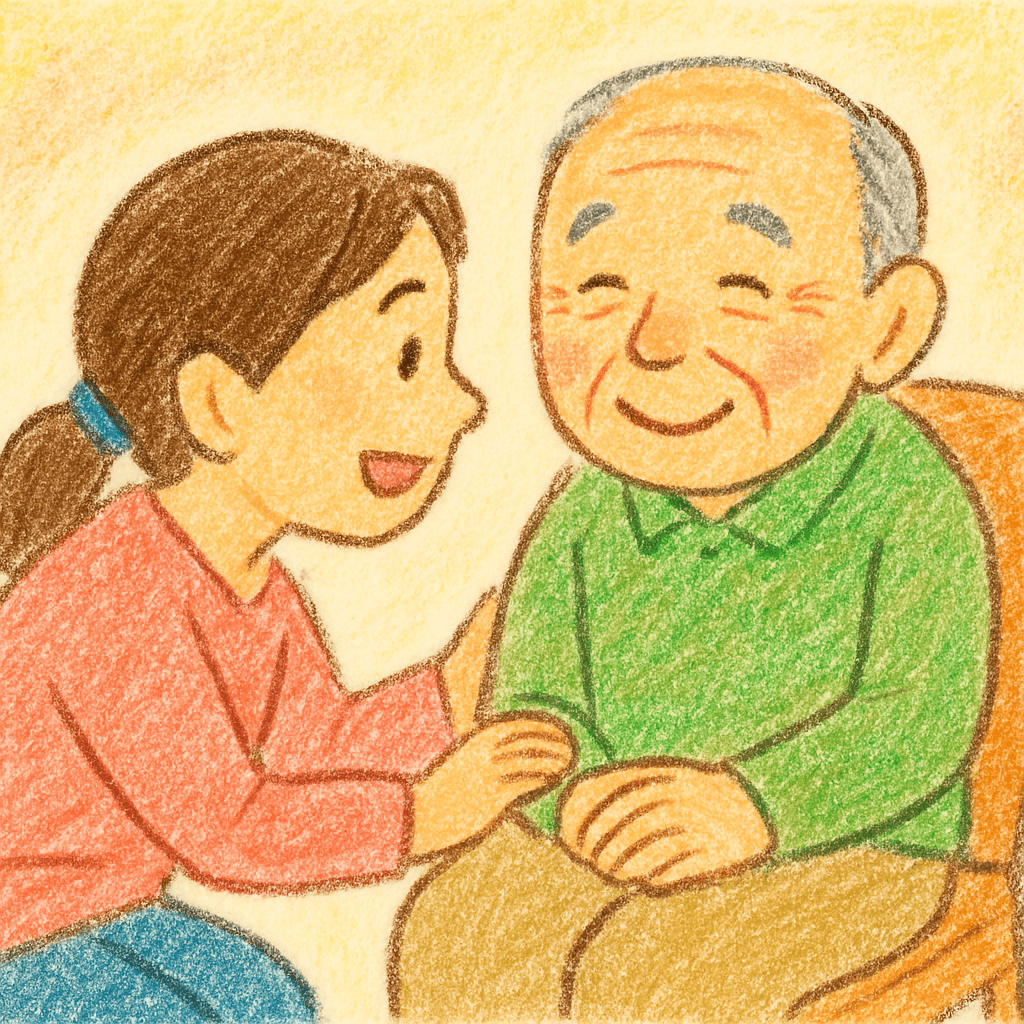
避難所のトイレは「公共的で落ち着かない」「行きにくい」と感じる方が多く、認知症の方には特に配慮が必要です。
● 色・音・香りを使って“トイレの場所”をわかりやすく
- 床に色付きテープで誘導ラインを貼る(黄色や赤など認識しやすい色)
- ポータブルトイレに布や模様をかけると、家庭のトイレのような安心感が生まれる
- 録音した「トイレの音」や本人の声をスマホで再生 → トイレの記憶を呼び起こす
- ラベンダーなど穏やかな香りを使うと、空間に安心感が出る
● プライバシーと静かな空間を確保する

- ついたて・段ボール・カーテンなどで目隠し
- 「トイレです」「ご自由にどうぞ」と貼り紙をつけて、誘導と安心感を与える
- 介助の声かけは、はっきり・やさしく・短く
認知症の人の在宅避難におけるトイレ支援と備え
自宅が使える場合でも、ライフラインが止まると排泄環境は激変します。
● トイレ動線を工夫してストレスを減らす
- 明かりの確保:懐中電灯・ソーラーライトを置いて不安を軽減
- 床にテープで誘導ラインを貼る(夜間でもわかるように)
- おしりふき・流せるシート・防水マットを常備
● “家庭のまま感”を意識する
- 見慣れたタオルやカバーをトイレ周りに使う
- お気に入りの香り・小物など「普段の安心」を再現
- 嫌がる場合は、トイレをお風呂に置きかえるなど柔軟に
家族・支援者にできる声かけと関わり方
避難所で周りの人にも伝えたいこと
避難所では、介護している本人だけでなく、周囲の人たちの理解もとても大切です。
認知症の症状は見た目ではわからないことも多く、誤解や不安を生まないためにも、さりげなく事情を伝えておくと安心です。
たとえば、こんな一言が効果的です。
- 「この人は認知症があって、慣れない場所で混乱しやすいんです」
- 「急に動いたり大きな声を出すかもしれませんが、ご理解いただけると助かります」
ほんの少しの共有が、お互いのストレスを減らし、やさしい空気を生みます。
避難所は知らない人同士が一緒に過ごす場所だからこそ、伝える勇気が大きな安心につながります。
認知症の方は、「行きたくない」「何をするかわからない」と感じやすい場面でも、やさしい誘導や言葉で行動できることがあります。
- 「トイレ行こうね」よりも「こっちでゆっくりしようか」など穏やかな誘導
- 「一緒に行こう」と声かけ+介助者が先に動く
- 視線を合わせず、横からそっと手を添えるだけでも安心感が生まれる
- トイレでうまくいったら「ありがとう」「助かったよ」と自然に褒める
まとめ|トイレ支援は“その人らしさ”を守るケア
トイレは「ただの用足し」ではなく、その人の尊厳を守る大切なケアのひとつです。
避難所でも在宅でも、少しの工夫とまなざしがあるだけで、認知症の方が安心して過ごせる環境は作れます。
🌸著者の声
現場で働いていて感じるのは、認知症の人はたとえ毎日過ごしている場所でも、
ふと「今どこにいるのかわからない」という不安に襲われることがあるということです。私自身はまだ認知症ではありませんが、
それでも、いつもと違う日常が訪れるだけで心がざわつくことがあります。だからこそ、できるだけ不安を取り除いてあげたい。
それが、私たち周りの支える側にできる大切なことだと思っています。
👉 寝たきりの方の災害時トイレ支援については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
【寝たきり家族の災害時トイレ支援ガイド】
👉 認知症の方が安心できるための工夫は、家族の備えや在宅介護の防災準備とも深く関係しています。
よろしければ、こちらの記事も参考にしてください。
介護福祉士として13年。防災や終活にも関心あり。
在宅ワークを目指して、パソコン奮闘中の「さっちん」です!